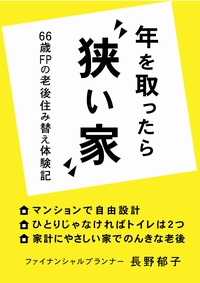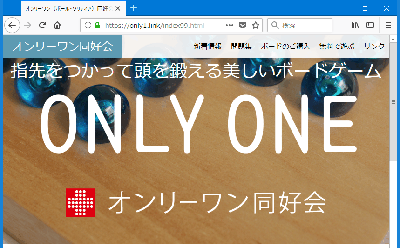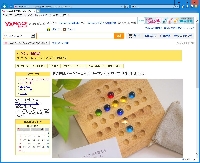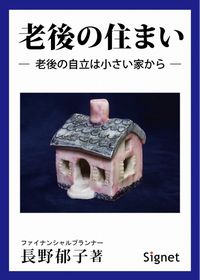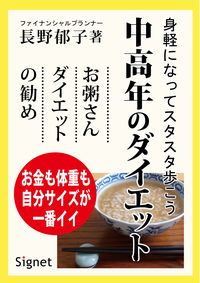相談員コラム…仕送りと生活保護から考える食費②
相談員コラム…仕送りと生活保護から考える食費②
前回は大学生の仕送りが減って、食費を切り詰めて1日700円ぐらい、一方生活保護の方の食費が1日1,300円ぐらいという話だった。この話は「もっと仕送りや奨学金の増額を」とか「もっと生活保護費を増やせ」と言う事では決してない。親だって精一杯仕送りしてるし、生活保護費だって政府の財政を考えれば増額はむずかしいだろう。この金額でやりくりするしか無いのだ。その中で豊かでおいしいごはんを毎日食べるには自分で作る=自炊が一番。「自立自活は自炊から」である。
経験的に自炊は安くておいしいと皆知っている。でも、具体的な数字は良く知らない。例えば、ごはん一杯の値段。普通茶碗でごはん一杯は150g(約250キロカロリー)、生米にすると65gになる。5Kgで2,000円のまずまずの等級のお米でも一杯当たり30円だ。食パンは総務省の家計調査で3枚79円、一枚当たり26円、158キロカロリー。うどん玉3つで110円、一玉37円である。例えば朝食パン一枚、昼食はうどん一杯、夕食はごはん一杯という主食なら、主食費で93円である。倍量食べても186円にしかならない。焼き肉屋さんの中ライスが130円、コンビニおにぎり110円に比べて、ごはん一杯30円の自炊はかなり安い。これなら、副菜を入れても700円でやっていけそうな気がする。
私が一人暮らしで自炊を始めた頃と決定的に違うのは、残ったごはん等は冷凍してレンジでチン出来ることだ。学生の頃、まじめに自炊をやろうとすると、冷蔵庫はあっても物の腐敗との戦いだった。今は何でも小分けして冷凍にしておけるので本当に無駄がない。ごはんも1度に3合炊いて、お茶碗一杯分ずつラップに包んで冷凍しておけば、一週間は心配ない。お肉だって閉店間際の安いときに大きなパックを買って、小分けして冷凍しておけば、野菜炒め、うどん、カレー、何にでも使える。ほうれん草も2束、3束のかご盛りを買ってきて、全部湯がいて水にさらして刻み、一握りずつしぼり冷凍しておく。麺類にいれたり、ごま和えにしたり、味噌汁に入れたり、ソテーして付け合わせにしたり重宝する。こうしたちょっとした自炊技術は何となく自然に覚えた。
そこで提案なのだが老若男女問わず、今まで自分でごはんを作った事のない人に、安くて簡単でおいしい自炊のやり方をキチンと教える場が欲しい。例えば大学が学生向けに定期的に料理教室を開催する。食パン6枚をいかに毎日変化をつけておいしく食べるかとか、めんつゆの活用法、冷凍や解凍の仕方、たっぷり野菜の取り方、カレーの作り方、チャーハンの作り方、おにぎりの結び方なんてのも良いかもしれない。
もちろん食材費は学校が出して、講師は学生でも良い。料理の出来ない子も多いが、得意な子も結構いる。一食浮くのでたぶん参加者は多いだろう。そしてそんな自炊レシピ集を新入生に配布する。豪華な大学パンフより絶対喜ばれる。自炊学生だけで無く、いずれ巣立つ若者が、手早く、美味しいものが作れたらどんなに本人のためになるだろう。親にしてみれば、そんなことしてくれる大学のポイントはかなり高い。
一方、生活保護の方の食費。私は金額の多寡より、その生活力が問題だと思う。ただ窓口の担当者が一人当たりで抱えている案件が多いため、丁寧な家計指導まで行なえないようだ。前回書いた生活保護の食費1日1300円は決して惨めな金額では無い。でも生活保護受給者の中でも、テレビなどで取り上げられる一人暮らしの高齢男性の食事風景は確かにわびしい。ごはんは炊いても、卵かけごはん、納豆ごはん、レトルトカレー、サカナの缶詰。若くても病気がちだったり、自炊のやり方を知らなかったりすると、出来合いの物や加工食品が多くなりがちだ。このような食生活、タマにならいいけど、毎日では惨めな気持ちになるし健康も損なうだろう。
でもここで必要なのはお金では無く知恵である。例えば行政主催が「おいしい節約自炊教室」を定期開催する。公民館や市民センターなどには台所があることが多いからその設備を利用し、ボランティアやシルバーセンターの方に講師をお願いすればそんなに費用もかからない。一般公開し、生活保護家庭に参加を義務づければイヤイヤでも自炊力はついてくる。若い受給者に自立を促すにも、生活保護の最重要課題である医療費を抑制するにも、きちんとした食生活は一番の近道だ。食べることは生きる活力につながる。
私は忙しい商家に生まれ、小学二年生の時には、ごはんと焼き魚、味噌汁という夕食が作れた。母親にやり方を教わり、見よう見まねで覚えた。料理なんて誰だって出来ると思っていたけど、確かに習う環境に無かった人が一人きりで自炊力を身につけるのは大変だ。でも、自分でごはんが作れるというのは、今回見たように食費が少ない人には文字通り死活問題だ。行政も漠然とした自立支援なんていわないで、自立・自活を支援する社会人の自炊教室はじめてくれないかなあ。
※前の記事は左の「相談員のコラム」で読めます。