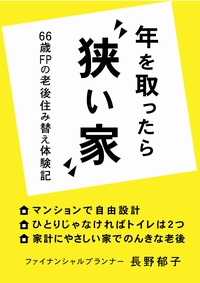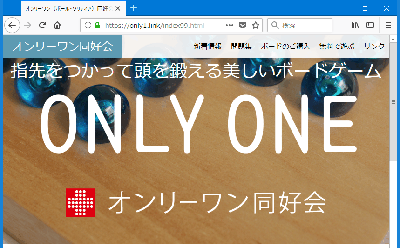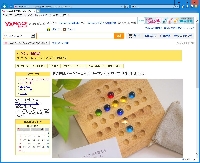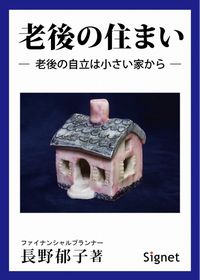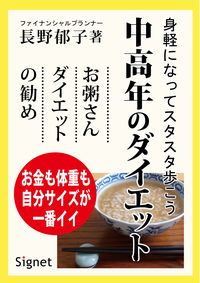相談員コラム…老後は都会で④ 人の多さ
相談員コラム…老後は都会で④ 人の多さ
実家に帰ったときに親しい人と話すと「東京はたまに遊びに行くならいいけど、人が多いから住むのはイヤ!」と眉をひそめる。たぶん、脳内には渋谷のスクランブル交差点や満員電車の映像がちらついているのだろう。私だって人混みはイヤだ。電車通勤をしなくなり数年たつ。たまに満員電車に乗るとめまいがする。ただ、電車だって一日中混雑している訳ではないし、老後の時間に余裕のある暮らしなら、混雑時を避け、場所を選べばそんなに人混みに出くわすことはない。
もうひとつ「都会の人はお隣と挨拶もしないんでしょ、そんな人情も無いところ住めない。」とも言われる。これほど、都会の人の多さは本当にイメージのように悪いことばかりなのか? 若くて働く場を求めて都会に来るのと違って、老後になって都会に住もういう人にとって「人の多さ」というのはどういうことなのか、今回はこのあたりを考えてみたい。
●人が多いのは人手が多いということ
老後といっても、仕事を引退してから本格的介護が必要となるまでに20年~30年の時間がある。この間、ちょっとの手助けがあれば老後生活はぐっと快適になる。都会はこの手助けを担う人が直接、間接、有料、無料を問わず多いのだ。
老後の助けは公助、共助、自助という。例えば「老後のひとり暮らしで倒れたらどうしよう」という不安には、区役所の地域包括センターに相談に行けば、緊急用通信機器を無料で貸してくれる(公助)。共助なら見守りをしてくれるボランティアのNPOもある。自助なら毎月費用はかかるが、ホームセキュリティの会社に頼めば、ボタン一つで駆けつけてくれる。食事を自分で作れなくなっても、外食や中食、宅配弁当など選択肢が多い。需要、供給ともに人が多いので選択肢も多い。
自分が出来なくなったことがあっても、ひとつひとつ人の手を借りて解決出来れば、老後の長い時間をかなり自立して過ごせる。60代70代で元気なら、逆に自分が人の手助けになることも可能だ。もちろん、本格的介護が必要になったら尚更、人手は必要だ。老後にまわりに人が多いというのはそれだけで吉だ。
●人づきあいと人の多さについて
人とのつきあい、特に他人とのつきあいは自分との距離感で決まる。挨拶もしない、目も合わさない全くの他人(これをA集団とする)、挨拶はするが相手はよく知らないレベルの他人(B集団)、相手が何者か知り、時候や当たり障りのない会話をする間柄=知人(C集団)、意見を交わし本音で話せる関係=友人(D集団)、お互いに理解し合い相談できる相手=親しい友人(E集団)、以上5つぐらいに分かれる。しかも、ハッキリとわかれるのでなく、微妙に入り組んだり、行ったり来たりする。
地方と都会の決定的違いはこの他人との距離感だ(あくまで私の経験なので気を悪くしないでほしい)。都会暮らしは人間関係が希薄といわれるが、地方の人間関係が親密といえるかは疑問だ。地方のコミュニティは狭く、長いつきあいなのでA集団はほとんど存在せず、C集団がほとんどだ。従って他人のスペック(本人の周辺情報)は実によく知っている。相手の親兄弟、親戚関係、学校、極端な事をいえば生活時間まで知っている。
ただし、それが本人を理解しているのとはちょっと違う。スペックはよく知っていても、本人が何を考えている人かは意外に知らない。閉鎖した小さなコミュニティでは決定的な人間関係の断絶を回避する傾向があり、意見をいわないのが美徳だ。だから、ほとんどの他人がCばかりで、相手が何を考えているのかわからないので、なかなかDやEにならない。こういう社会の人間関係は安定していても息苦しい。
一方、都会は圧倒的にAが多い。外に出れば道ですれ違う人も電車で隣り合う人もほとんどの人がA集団、都会だってご近所の顔見知りには挨拶ぐらいするが、無用な詮索はお互いにしない。基本的に見ず知らずの他人の中で暮らしている。人間関係が希薄といわれればその通りである。
もちろん仕事関係や知人程度のCの関係はいる。ただ趣味や職場の仲間、学校時代の知り合いなどは親しいが、全部が全部何でも言えるという間柄ではないし、部分的なお付き合いが多い。大昔、職場の上司に「政治と宗教の話をしないのが大人のマナーだ。話題はスポーツにしろ。」と言われてカチンときたが、結局、C集団の中では当たり障りのない話題に終始するしかないと今ならわかる。それでも少人数ながらDやEの友人はいる。
Cの関係からDやEにもっていくには単に気が合うだけで無く、最低限「自分の思うところ」を言う必要があると思う。別に意見の一致は必要ないが、相手が何を考えている人間かがわからないと私はなかなか友達にはなれないのである。そうして今も続く友人が出来たことが東京で暮らした一番の収穫である。たぶん東京に来なかったら出会えなかった人たちだ。
都会の人の多さはこの人間関係の分母の多さでもある。都会といってもしょせん小さな社会の集まりだ。ただ、地方の小さな社会だと「自分の思うところ」を言ったがために、排除されると行き場がないが、小さな社会がたくさんある都会なら、ひとつでダメなら別に行けばいい。逃げ道があるので意見も言いやすい。人づきあいのやり直しがきくのが都会の人の多さの良いところだ。
また人の多さ=分母の多さは、少数派に住みやすい。地方なら孤立し、肩身が狭い思いをする少数派でも分母が多ければ必ず仲間は見つかる。
人づきあいの難しさや煩わしさ、楽しさや喜びは基本的に地方でも都会でも同じだ。思うに老後は華やかな人づきあいは必要ないが、数人の友達がいてくれたらぐっと豊かになる。
都会の人の多さはたまに来る人にとっては辟易とするだろうが、住めば都とはよく言ったもので、住んでしまえばそんなに気にならない。むしろ、老後の生活や人づきあいにとって、人の多さは選択肢の多さや多様性の豊かさなどプラスとなるのではないだろうか。
次回はしがらみのない都会生活を考える。
※前の記事は左の「相談員のコラム」で読めます。