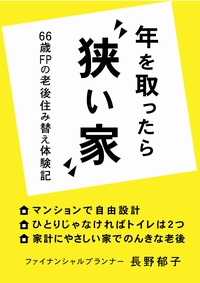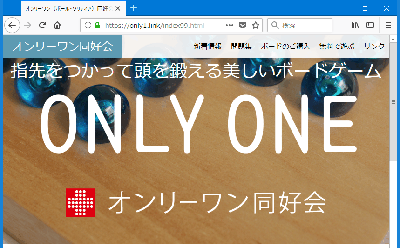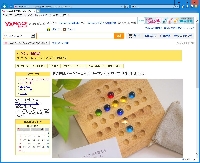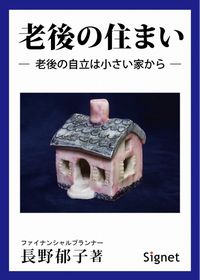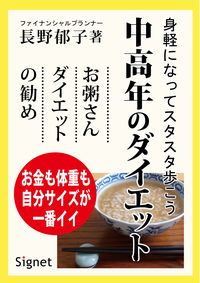相談員コラム… 老後は都会で⑤ しがらみのない生き方
相談員コラム… 老後は都会で⑤ しがらみのない生き方
都会人は根無し草と言われる。若い頃、進学だったり、仕事を求めたりして都会に来る人はほとんど単身者であって、身近に家族や親戚など縁者が居ないからだろう。言わば義理の関係のない身軽な独り者だ。老後に都会に来ようという人もたぶん単身者が多い。根無し草は不安定だが、一方で種や胞子になって飛んで行くことができ、どこにでも根付ける自由さがある。
私も地方の実家で暮らしていた10代の頃は「○○さんちの○○ちゃん」だった。商家なので家族だけでなく、親戚、ご近所、お客さん、従業員の方、とにかくまわりは知り合いだらけ。それが当たり前の世界だったのと、他所から嫁いだ母が馴染むのに苦労するのを見ていたので、その環境に過剰適応していた。あのまま実家の近くで就職し、結婚し、出産していたら○○で働く、○○の妻で、○○のお母さんになっていただろう。まわりの視線の重圧そのものよりも、それに反発し疲弊したり、自己規制したりする自分に嫌気がさしていただろう。
都会だって“役割でしか人を見ない”そんな側面も無いことはないが、地方のように四六時中、どこででもそういう視線にさらされ続けるということはない。都会では、ひとりで出かければ、まわりは知らない人だらけ、誰も気にとめないし、どこの何々という人もいない。都会生活の良さはしがらみの無い生き方ができることだ。この人目を気にしない生活がどれだけ自由ですがすがしいことかは経験した人にしかわからない。窮屈な暮らしというのは、窮屈なものを脱ぎ捨てたときに初めてわかる。
私の知り合いに退職してから東京に転居してきた人がいる。地方の狭い町で教員をしていたので、町中に教え子やその親たちがあふれ、どこに行っても知り合いだらけで、スーパーで何を買ったのかもまわりがわかってしまう世界だった。仕事を辞めても「先生」と呼ばれ、何をするのもまわりを気にして自己規制、行くところは無難な図書館ぐらいだし、つきあうのは親戚や昔の同僚だけ。こんな生活して人生を終わるのかと思ったらたまらなくなり「そういえば大学卒業したとき、もっと東京に居たかったけど、親にいわれて帰ったんだ。もう親もいないし職場に行く必要も無い。そうだ東京に行こう。」と思ったそうだ。
田舎の家はそのままにして、土地勘のある母校の近くにアパートを借り、年金と退職金を持って東京に来た。元々まじめなので、東京に来たからといっていきなり弾けた生活をする訳ではない。母校の公開講座に行ったり、卒業生特典を生かして図書館や学食、スポーツ施設に行ったり、昔の友人と旧交を温めている。ただ、まわりの目がないというのがこんなにも気が楽だとは思わなかったと言って、どこに行くのも楽しそうだ。この間は誘われて初めてランチの昼ビールを経験したと言っていたし、一度パチンコをしてみたいのでつれてってくれと言われている。こんな些細なことすら人目が気になって出来なかったのだと思う。これは彼女が東京に来ることで得られた小さな「解放」「自由」だ。
60歳目前になって思うのだが、いわゆる「しがらみ」のある人たちと当たり障りの無い意味の無い会話を延々して「いい人」をやっている時間はもはや私にはない。世の中にはどうしてもわかり合えない人、義理でイヤイヤつきあう関係など煩わしい人間関係はある。若い時は、同じ意見の人とばかりつき合うのではなく、意見の違う人とこそつきあうべきだと思っていた。もちろん今でもそう思うが、老境にさしかかる年になると残された時間がとても貴重で大事に思えてくる。
他人の視線=世間体を気にすることなく、やりたいことをやり、楽しいと思える時間をいかに過ごすかが老後の最重要課題だ。だから「老後」に思い切って都会に来ることで、しがらみを断ち切り、一度人づきあいをリセットするのもいい。それでもつながる関係が本当の関係だろう。
次回は老後の自由な時間についてである。
※前の記事は左の「相談員のコラム」で読めます。